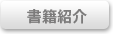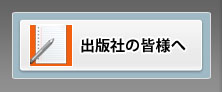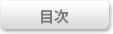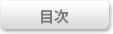
プロローグ
第一章●栽培編
1 ボルドーのブドウ品種
栽培面積の89%が「赤」ワイン用
主要品種はマルベックとカルムネールだった
複数品種がリスクヘッジと味わいの相乗効果をもたらす
2 冬の作業
カラソナージュ…支柱を土に打ち込む作業
カラソンは結局アカシアに戻った
カベルネ・ソーヴィニヨンの枝は固い
メルロの強い生命力
3 コンタージュと収量制限
開花期の天候は影響が大きい
戦略的なコンタージュ
飛び散る花粉をものともせず
摘房作業で剪定の重要性を実感
低収量と収量制限はおなじではない
4 糖度調査~収穫日の決定
ボルドーの夏は10時過ぎまで明るい
8月下旬、糖度調査を始める
分析センターの大きな役割
「完熟まで待ちたい」vs「雨の前に収穫したい」
ブドウの熟度は太陽からしか得られない
5 ヴィンテージ
天候がワインのスタイルを決める
日本ワインのヴィンテージは肌で感じたもの
産地ごとにミレジムの評価は異なる
第二章●醸造編
1 収穫~発酵前浸漬まで
落ちつかない収穫前夜
手収穫がいつも最良とは限らない
選果台の役割は大きい
一年の苦労が報われる瞬間
果汁の温度を下げる
発酵前に「醸し」を行う
2 ルモンタージュと圧搾
赤ワイン醸造の決め手はルモンタージュ
ルモンタージュの効果はタンク容量や発酵の度合いで異なる
引き抜きは重力を利用する
カス出し作業はみんな大好き
圧搾ではカスをやさしく扱う
最上の区画は新樽でマロラクティック発酵
バーベキューで打ち上げパーティー
3 樽の仕事
「熟成」の概念はいつ生まれたか?
船の大きさを表す国際単位はワイン樽に由来する
ぶどうを「ワイン」にして格納する
樽で育成するワインの滓引きは慎重に行う
ワイン産地ならではの中古樽マーケット
樽メーカーとワインの相性を探る
「この樽貯蔵庫、わくわくするよ!」
4 樽の個性
オーク材にもいろいろある
樽は2年使うと重くなる
樽は重要なバイプレイヤー
樽香の成分にはどんなものがあるか?
シーズニングはオーク材を洗濯するプロセス
トースティングは軽くこがす程度で
大切なのは果実香と樽香のバランス
5 ワインの貯蔵
ワインにとって亜硫酸は重要なもの
四つの顔をもつ亜硫酸
赤ワインのフェノレは「動物臭」
ブレタノミセスの増殖を防ぐ確実な貯酒管理
白ワインのフェノレは薬品的なニュアンス
6 温故知新
「時間」のフィルター
梗は徹底的に取りのぞく
最上のプレスワインを得る圧搾機とは?
発酵槽も木桶に回帰している
100年以上前からあった滓引きの方法
歴史を知ることで未来を予測する
第三章●改植編
1 土壌調査
改植は多額の費用がかかる大きな投資
メルロよりカベルネを先に改植する
まずは土壌をよく知ることから
ショネ博士の土質地図
診断をもとに土壌を改良する
2 樹の引き抜きと再植
引き抜き開始
畑から水を抜く排水路を設置する
苗植えの機械で正確に定植する
3 ブドウ品種とクローン選抜
ブドウ品種の多様性
「品種(セパージュ)」という概念
クローンとは、おなじ品種における性質の違い
優秀なクローンを選抜する
クローン全盛に対する反省
4 各品種の状況
自国のテロワールでクローン選抜を行う時代に
ピノ・ノワールの場合
ピノ・ノワールのクローンの変遷
サンジョベーゼの場合
ボルドー品種の場合
甲州の場合
5 台木について
フィロキセラ対策
台木の三大原種
交雑で生まれたいろいろな台木
カリフォルニアの油断
台木の働きは車のエンジン
6 植栽密度
昔は垣根式ではなかった
垣根栽培に移行した二つのステップ
ギヨ式とコルドン式
品種と台木は好みと勘で選んではいけない
第四章●歴史編
1 古代~ローマ時代
ボルドーの地勢
テロワールとはなにか?
ブドウ栽培に理想的な土地?
ボルドーにおけるブドウ栽培の開始
ゲルマン人の支配下、ブドウ栽培は衰退
2 イギリス王室とボルドー
ノルマンディー公、イングランド王となる
女傑アリエノールの野望
ボルドーのライバル、ポワトゥーの台頭
欠地王ジョン1世、大陸の領土の大部分を失う
フランスと決別し、ボルドーワインの名声が高まる
3 ボルドー特権
英仏百年戦争の始まり
上流のワイン産地を排除するボルドー特権
新酒はロンドンを目指した
メドックをおさえ利権を守ったボルドー
ボルドー特権はさらに300年も維持された
〈コラム〉 「ヴィンテージ」という概念
4 高級ワインの登場
甘口白ワインを求めたオランダ人
ブランデーの技術導入
可能性を秘めた新しい産地、メドックの登場
最初に有名になった「オー・ブリオン」
裕福な貴族階級に愛されたニュー・フレンチ・クラレット
イギリスとフランスの通商
1855年の格付けはパリ万博がきっかけ
ナポレオン3世はボルドー好き?
ボルドー、空前のワイン好景気を迎える
〈コラム〉 入市税
〈コラム〉 1973年の一級再格付け
5 新大陸からの病虫害
三大病虫害によりブドウ畑が壊滅
ボルドー液は「泥棒よけ」から
フィロキセラはゆっくりと広がり、最悪の被害に
対策1 アメリカ系品種を交雑する
対策2 アメリカ系ブドウを台木にする
〈コラム〉 台木への接ぎ木
6 消えたワイン産地
日本人留学生が見た産地は消滅した
赤ワイン用品種の交代
〈コラム〉 新天地を得たフィロキセラ以前のボルドー品種
7 原産地統制呼称法AOCの成立
ブドウ生産者の強い要望で誕生
評価はブラインドの官能検査で
規制だけでなくプロモーションも大切
8 「歴史編」まとめ
〈コラム〉 ワイン教育・研究の新展開 ボルドー大学
第五章●テイスティング編
1 ボルドー大学のテイスティング教育
テイスティングの起源はギリシア時代に
歴史あるテイスティング講座「DUAD」
香りの標準化合物を使うテイスティング実習
2 閾値を意識する
閾値は人によって違う
化合物ごとに自分の感度を知っておく
まぐれあたりを減らす三点識別法
審査員を審査すれば、より客観的な審査が可能になる
3 客観的なテイスティング
先入観の影響を知るためのテイスティング
醸造家のテイスティングは客観的・分析的であるべき
順番によって味わいや香りの感じ方は変わる
4 実戦的なテイスティング
難しいと感じたときのテイスティング・テクニック
白ワインのアッサンブラージュを実際に試して学ぶ
グランヴァンで成熟したタンニンを実感する
ファーストワインとセカンドラベルを決めるのは経営戦略
産地が発展するにはテイスティング教育が重要
5 公開テイスティング
新酒を先物買いする「プリムール買い」というシステム
シャトーで行われるプリムール・テイスティング
ボルドーの各AOCでは、年に一回の一般公開日を設けている
足を運んでみてわかることは多い
ソーテルヌの一級シャトーが国立の醸造学校に
6 ワインコンクール
シタデル国際ワインコンクールに審査員として参加する
審査は感覚が鋭敏な午前中に
ワインはバランスが大切
第六章●生活編
1 ボルドーの食材
美食の国フランス
ジロンド河を上ってくるアロウズという魚
ジロンド川の汽水域がもたらす美味、キャビアとヤツメウナギ
卵白はワインに、卵黄はカヌレに
2 食材ショッピング
スーパーマーケットは食材のワンダーランド
アルカション湾名産の牡蠣もボルドーの楽しみ
半期に一度のバーゲンでワインをまとめ買い
3 キノコ狩り
皆が夢中になるセップ・ド・ボルドー
ブドウ畑で見つけたムスロン
4 ビストロと家庭料理
芽吹きを見にサンテミリオンへ
ブドウ畑の中のビストロ
食事とワインのよい関係
ホームステイで経験したフランスの家庭料理
シャラント地方、美味なる休日の過ごし方
5 メドック・マラソン
赤ワインを飲みながら走る?
完走目指してワインはお預け
牡蠣、ステーキ、チーズ…補給所でコース料理
エピローグ
1 アウトソーシング
ボルドーでは圧搾機もレンタルできる
効率よくフル稼働するレンタル機材
レンタル用の移動式ビン詰めライン
各種の分析なども外注できる
マーケティングはネゴシアンが担う
2 ワイン産地について
身の毛のよだつ急斜面
天候よりも大事なもの
日本でワインを造る理由
日本ワインの未来を切り拓く
あとがき